
室生寺

女人禁制だった高野山に対し、女性の参詣が許されていたことから「女人高野」の別名があり、現在は石楠花(しゃくなげ)の名所としても知られています。
奈良時代末期の宝亀(ほうき)年間(770年~781年)、東宮山部親王(とうぐうのやまべのしんのう・のちの桓武天皇)の病気平癒のため、室生の地において延命の祈祷したところ、龍神の力でみごとに回復したので、興福寺の僧・賢璟(けんけい)が朝廷の命でここに寺院を造ることになったといわれています。
現存の室生寺の堂塔のうち、創建頃(9世紀前半)にまで遡ると見られるのは五重塔のみであり、現在のような伽藍が整うまでには相当の年数を要したものと思われます。
室生寺の四至には「門」を設けており、田口の長楽寺を東門、大野の大野寺を西門、赤埴の佛隆寺を南門、名張の丈六寺を北門としています。
室生寺は長らく興福寺との関係がありましたが、元禄7年(1694)、真言僧・隆光(りゅうこう)が興福寺に室生寺の分離を要求し、元禄11年(1698)には興福寺から独立して真言宗寺院となりました。その後、江戸幕府5代将軍徳川綱吉の母・桂昌院(けいしょういん)の寄進によって山内の堂塔が修理されています。昭和39年(1964)には、真言宗豊山(ぶざん)派より独立して真言宗室生寺派の大本山となり、現在に至っています。
境内の建物や仏像の多くは、国宝や重要文化財等に指定されており、なかでも国宝の五重塔は屋外の五重塔では日本最小として知られています。
\ 詳細はこちら /
BBQ あまご お伊勢参り お土産 きのこ料理 そば つつじ やまとの水 カフェ キャンプ ハイキング マラソン大会 ライトアップ 仏像 伊勢本街道 伊勢街道 佛隆寺 古事記 史跡 合宿 吉野葛たあめん 地元野菜 宿泊 山の幸 彼岸花 木製品 木造如来坐像 柿の葉寿司 桜 氷の華 滝 無添加 特産品 獅子舞 登山 秋まつり 紅葉 絶景 蛍 道の駅 重要文化財 霧氷 露天風呂 鮎釣り 龍神伝説


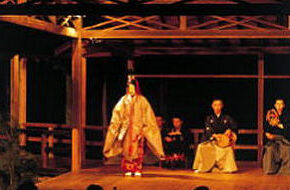

-1450x930.jpg)
